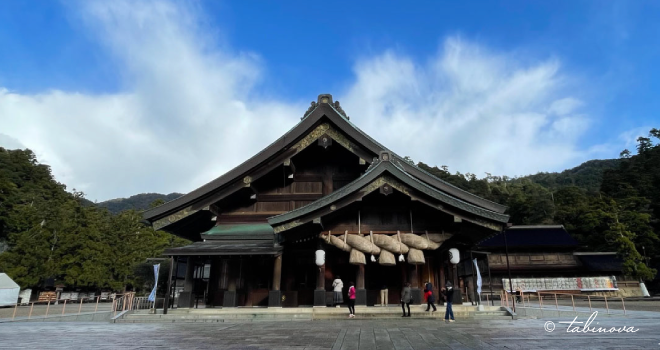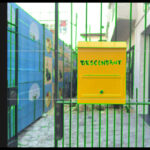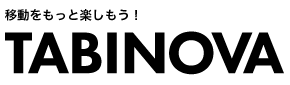たった一区間のために開発されたEF63
かつての信越本線には一駅の間だけ機関車の助けを借りながら列車が峠を越えていた場所があります。群馬県と長野県の県境に位置する信越本線の碓氷峠です。
横川駅と軽井沢駅の間のわずか一区間11.2kmですが、この区間だけ機関車がすべての列車に連結され登り降りを助けていました。

66.7‰の急勾配を越える
この場所の勾配は66.7‰(パーミル)。これは1000m進むと66.7m登っているという意味です。
角度にすると4度ほどなのですが、鉄道にとってはかなりの急勾配となり、実際にこの区間を走っていた特急あさまの先頭と最後尾ではビルの1階と5階ほどの高低差が出ていました。ここまでの勾配だと通常の列車ではとても登り降りできないため、EF63というこの一区間の為だけに開発された特殊な電気機関車2両を必ず下り側に連結して峠を越えていました。
新幹線開業前は関東と信州、北陸を結ぶ大動脈としてこの場所を毎日多くの列車が走っていましたが、その全てがこのようにして峠を越えていたので、最寄りの駅では連結、切り離し作業がひっきりなしに行われていたことになります。
停車時間を有効活用して人気を博した駅弁

そのため駅での停車時間が長くなっていたのですが、その時間を利用して人気が出たのが横川駅名物峠の釜飯です。
列車が入ってくるたびに多勢の売り子さんがホームに出てきて停車時間を利用して乗客に釜飯を販売していました。
この信越本線の横川ー軽井沢間は残念ながら1997年10月の長野新幹線開業とともに廃止されてしまい、今ではこうした光景を見ることができませんが、峠の釜飯は今でも人気の駅弁として横川駅や近くのサービスエリア、高崎駅などで購入することができます。
当時に想いを馳せながら駅弁を頂いてみてはいかがでしょうか?
tainovaのYouTubeチャンネルでも配信しています。よろしければフォローお願いします!