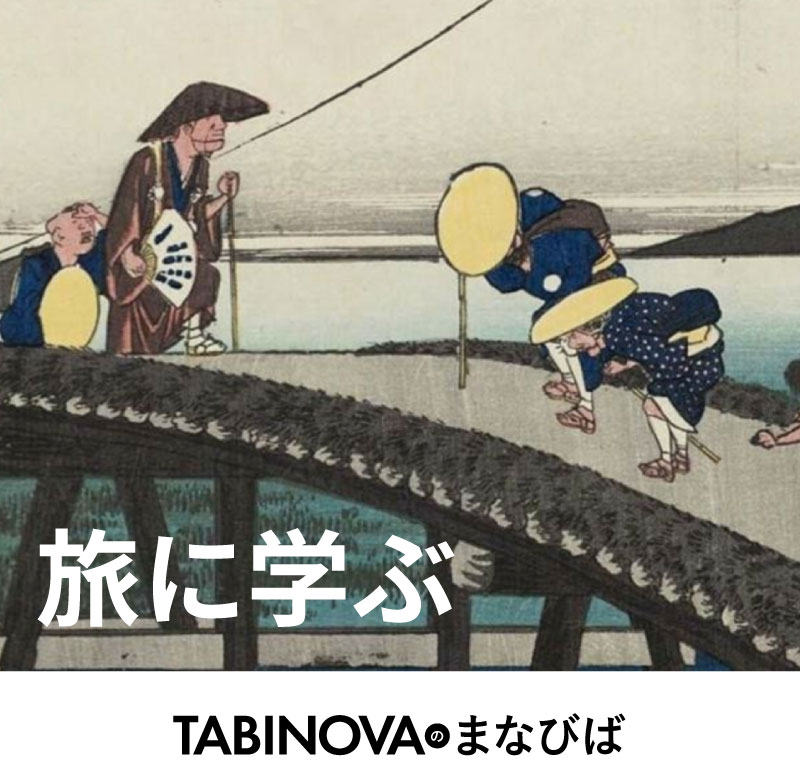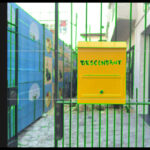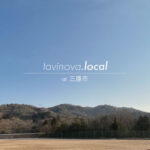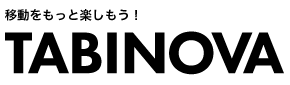全国各地には下水道の水路になったり、埋め立てられたりしてなくなった河川があります。特に東京都はその数が多く、暗渠(あんきょ)と呼ばれる、河川に蓋をして地下に埋め、今では緑道となっている廃河川が幾つかあります。
暗渠化した後の特徴とは?
暗渠化され、緑道などに変わった河川の特徴は、両脇の建物が背を向けていたり、道幅が一定ではなく、上流の方が狭かったり、中流、下流の方に行くと緑道と通常の道路が併走していたりと少し景色が広がるなどしています。
また、かつて生活用水として生活の中に溶け込んでいた小さい川には多くの橋が架けられていて、暗渠化され、緑道となった今でも横断する道には橋の名前が記されています。
暗渠した河川の特徴
- 緑道となって利用されている
- 両脇の建物が背を向けている
- 道幅はほぼ当時の河川だった時と同じ
- 橋の名前が残っている
東京に暗渠が多い背景とは? – 歴史を語り継ぐ場所
東京都の中小河川の暗渠化が進んだ背景は、戦前の震災や戦災からの復興の際、多くの瓦礫を処分するために埋め立てられたことや、戦後の高度成長期に急速に豊かになる都民の生活に下水処理が追いつかなくなっていたこと、汚染が進み川としての景観に問題が出てきたことなどがあるそうです。東京オリンピック開催に伴って、街の景観を整えたい思いもあったのかもしれませんね。


川だった時を想像しながら散策してみる
暗渠化され、緑道となった道を歩いてみると、河川だった頃の面影や特徴が見えてきます。普段何気なく利用している近所の緑道も、もしかしたらかつて生活の一部となって溶け込んでいた河川だったかもしれません。
こういった特徴を意識して、暗渠化された河川を巡り、歩いてみると、その土地の古くからの歴史を感じることができます。神社の場所と照らし合わせて見てみても、昔の生活、行動が見えてきて面白いと思います。